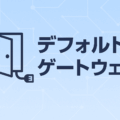目次
ルーティングとは?静的ルートと動的ルートをわかりやすく解説
どうも!リョクちゃです!
本編から更に少し進んだネットワーク技術、用語を紹介していきます。
➡ 前回:OSI参照モデルとは?7階層の仕組みと障害切り分けの考え方
IPアドレスやゲートウェイの仕組みを理解したら、次のステップは ルーティング です。
「ルータはどうやって行き先を決めているのか?」を知ると、ネットワーク全体の仕組みが見えてきます。
スポンサーリンク
ルーティングとは?
- 異なるネットワーク間の通信を中継する仕組み
- ルータやL3スイッチが「宛先IP」をもとに経路を選択する
👉 例えると…
- 「IPアドレス=住所」
- 「ルーティング=地図を見て最適な道を決める」
ルーティングの種類
静的ルーティング(Static Route)
- 管理者が手動でルートを設定
- 小規模ネットワーク向け
- メリット:シンプル、制御しやすい
- デメリット:障害時に自動切替ができない
例(Cisco IOS):
|
1 2 |
ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.1.254 |
動的ルーティング(Dynamic Route)
- ルータ同士が経路情報を交換し、自動的に経路を決定
- 大規模ネットワークや変化の多い環境で有効
主なプロトコル:
- RIP:小規模向け、ホップ数ベース
- OSPF:階層化に対応、中~大規模で利用
- BGP:インターネットの基幹で利用
実務でのルーティングの重要性
- 拠点間ネットワークで必須
- ルーティング設定ミスがあると「LAN内はOKだが拠点間通信できない」状態になる
- 冗長化(複数ルートを持たせる)で可用性を確保できる
実務トラブル例と対策
ルート未設定
- 症状:あるネットワークに到達できない
- 対策:静的ルートを追加、または動的ルーティング導入
経路ループ
- 症状:パケットが同じルータ間をぐるぐる回る
- 対策:ルーティングテーブルを確認、メトリック調整
冗長ルート不備
- 症状:1台のルータ故障で通信断
- 対策:冗長化(OSPFやVRRP併用)
資格試験での要点
- 基本情報技術者試験
静的ルートと動的ルートの違いを理解しているか CCNA
ip routeの構文、OSPFやRIPの仕組みが出題されやすい
まとめ
- ルーティング=異なるネットワークをつなぐ仕組み
- 静的ルート:シンプルだが冗長性なし
- 動的ルート:柔軟だが仕組みを理解する必要あり
- 実務では「未設定・ループ・冗長化不足」がトラブルの典型
👉 次回は 「ルーティングテーブル」 を取り上げます。 ルータがどんな基準で経路を選んでいるのか、テーブルの読み方から解説します。