目次
OSI参照モデルとは?通信の階層を理解して障害切り分けに役立てよう
どうも!リョクちゃです。
ネットワークの学習やトラブルシュートで必ず登場するのが OSI参照モデル。
7階層に分けて通信を理解します。
スポンサーリンク
OSI参照モデルの7階層
- 物理層(ケーブル、信号)
- データリンク層(MACアドレス、スイッチ)
- ネットワーク層(IP、ルータ)
- トランスポート層(TCP/UDP、ポート番号)
- セッション層(通信の開始・終了管理)
- プレゼンテーション層(データ形式変換)
- アプリケーション層(HTTP、メール、FTPなど)
図解でイメージするOSI参照モデル
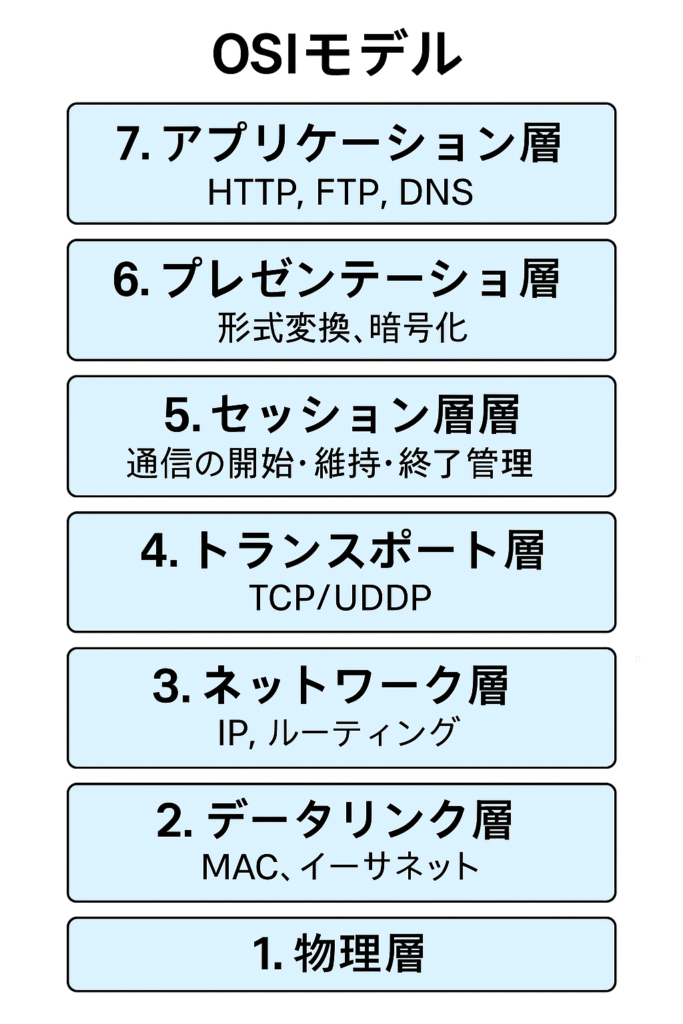
👉 各層は独立しており、「どの階層で問題が起きているか」を切り分けやすくする考え方です。
TCP/IPモデルとの違い
実際のインターネット通信で使われているのは TCP/IPモデル(4階層) です。
OSIモデルは理解のためのフレームワーク、TCP/IPは実装に基づくモデルと考えるとわかりやすいです。
| OSI参照モデル | TCP/IP階層 | 例 |
|---|---|---|
| 7. アプリケーション層 | アプリケーション層 | HTTP, FTP, DNS |
| 6. プレゼンテーション層 | アプリケーション層 | 暗号化, 文字コード変換 |
| 5. セッション層 | アプリケーション層 | セッション管理 |
| 4. トランスポート層 | トランスポート層 | TCP, UDP |
| 3. ネットワーク層 | インターネット層 | IP, ICMP |
| 2. データリンク層 | ネットワークインタフェース層 | Ethernet, PPP |
| 1. 物理層 | ネットワークインタフェース層 | ケーブル, 無線 |
図解でイメージするTCP/IPモデルとの違い
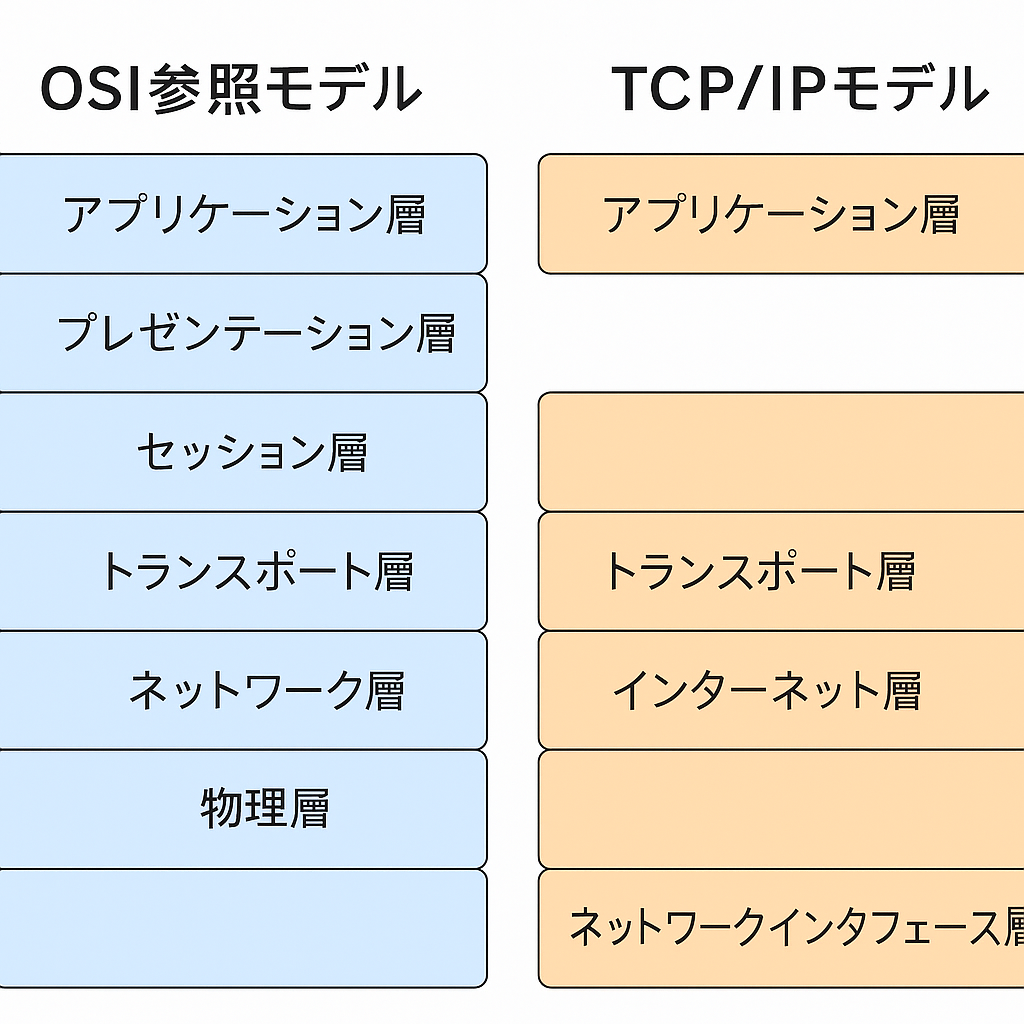
実務での活用例
- pingが通らない → L3の問題(IP、ルーティング)
- ブラウザだけ通信できない → L7の問題(アプリケーション)
👉 OSIモデルを理解していると、「どの層で問題が起きているのか」を素早く絞り込めます。
雑学:OSIとTCP/IP、どちらが先?
- TCP/IPモデル(ARPANETでの実用が先、1970年代)
- OSI参照モデル(ISOが理論を整理、1980年代)
つまり歴史的には TCP/IPが先、OSIは後から理論的に体系化された という流れです。
そのため、OSIは「学習・整理のための共通言語」として現在も利用されています。
まとめ
- OSI参照モデルは通信を7階層に分けた考え方
- TCP/IPモデルとの対応を理解すると実務に役立つ
- 障害切り分けの「思考の軸」として実務で必須
- 歴史的にはTCP/IPが先に登場し、その後にOSIで理論化された
関連記事
➡ 前回:NATとは?プライベートIPとグローバルIPを変換する仕組みを解説
ネットワーク基礎編まとめ記事はこちら
👉 【ネットワーク基礎編まとめ】初心者から学ぶOSI参照モデルまでの全記事リンク集




